個人再生の失敗原因は?失敗するとどうなるかも知りたい!

個人再生を利用すると借金額を大幅に減額できるので借金問題解決にはとても有効です。
しかし、個人再生も失敗することがあります。
今回、個人再生の失敗原因と、失敗するとどうなるかについて解説します。
個人再生が失敗する原因は「支払いが出来ない」

よくあるケースとして、支払いが出来ない場合が挙げられます。
個人再生では、借入金の減額は出来ますが、減額するにも限度がありますし、定められた借金の残金については確実に支払っていかないといけません。
個人再生の手続き中、裁判所も、依頼者が3年間の返済を継続できるだけの十分な収入があるかどうかについて審査します。
審査の方法としては給与明細や確定申告書、所得証明書などを確認します。
しかし収入が少なすぎるなどの問題があり、再生計画案に記載した支払いを到底継続していける可能性がない場合には、そもそもその再生計画案は認可されないのです。
このような場合は、個人再生手続きをそれ以上継続することが出来ず、失敗します。
個人再生が失敗する原因は「債権者が反対する」

個人再生が失敗するもう一つの主な原因に、債権者が再生計画案に反対するというケースがあります。
再生計画案は、借金の返済計画を定めて再生債務者が提出するものですが、過半数の債権者が異議を出したり、債権額の過半数を有する債権者が異議を出した場合には、その再生計画は認可されません。
このようなケースにおいても、それ以上その個人再生手続きをすすめることは出来ず、個人再生が失敗してしまいます。
個人再生手続きを成功させたいなら、各債権者が納得できるような内容の再生計画案を考えて提出する必要があるのです。
その他、不正な方法で再生計画案の認可決定を受けた場合などには、再生計画認可決定後にその認可決定が取り消されることもあります。
このような場合も、個人再生が失敗することになってしまいます。
当然のことですが、個人再生手続きをする場合には、財産隠しをしたり虚偽申告をするなどの不正をすることのないようくれぐれも注意が必要です。
個人再生が失敗したら自己破産!
では、個人再生が失敗したら一体どうなってしまうのでしょうか。
この質問は、弁護士の相談窓口などにおいても非常によくある相談内容です。
個人再生が失敗するということは、そもそも借金の減額がなかったことになるということです。
もちろん、高額な利息や遅延損害金もかかり続けている状態に戻ってしまいます。
このような状態に戻ってしまったら、通常はもはやそれ以上支払いを継続していくことは不可能です。
よって、個人再生に失敗した場合には、ほとんどの場合、自己破産手続きを利用して免責を得て、借金額を0にしてもらう他ありません。
これは、個人再生後定められた支払いが出来なくなってしまった場合も同様です。
借金の4分の3以上を返済済みであるなど、厳しい条件をクリアすればハードシップ免責などで借金を無くしてもらうことも可能ですが、ほとんどのケースではハードシップ免責の適用は難しいです。
個人再生に失敗したら、自己破産するしかなくなるということはしっかり心に留めておきましょう。
個人再生で失敗しないためには?
個人再生に強い弁護士事務所に依頼しましょう。
書類作成が素人には難しい一方で、専門家なら失敗しないコツを知っているからです。
おすすめの弁護士事務所は、正木絢生弁護士が代表を務める弁護士法人ユア・エースです。

フジテレビ『バイキングMORE』などメディアでも多数紹介されており、個人再生に強く信頼性も高いです。
また、匿名OK・10秒で完了する簡単なアンケートに答えるだけで向こうから連絡してくれて、完全無料で相談に乗ってくれるので、心理的なハードルも低いです。
以下のアンケートに答えて、一刻も早く、借金問題の苦しみから解放され、気持ちをラクにされてください。
個人再生(個人民事再生)は、債務整理手続きの一種です。
裁判所に申し立てをして、借金の金額を大幅に減額してもらい、決まった金額を原則3年間、債権者らに対して弁済していく手続きです。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類があり、手続き中2回、官報に氏名等が掲載されます。
小規模個人再生は職業に制限はなく、個人事業主や農業、漁業などでも可能です。
給与所得者等再生は会社員の場合に適用することができます。
給与所得者等再生の場合、可処分所得要件というものがあり、小規模個人再生よりも最終的な返済額が高額となってしまう場合があります。
とはいえ、任意整理と違って借金額を大幅に減額出来るメリットがありますし、自己破産のように財産を手放すデメリットもありません。
住宅ローン支払い中の場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)をつけることによって、マイホームを守ることもできますし、過払い金を回収したら、過払い金を手元に置いておくことも可能です。
このようにメリットの大きい個人再生ですが、失敗することがあります。
裁判所に再生計画案を提出し、その計画案について認可決定を出してもらうことが目的で、通常は数十万円の費用を払って弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手続きします。

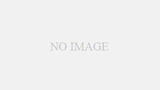
コメント